BLOG
 最終更新日:
最終更新日:
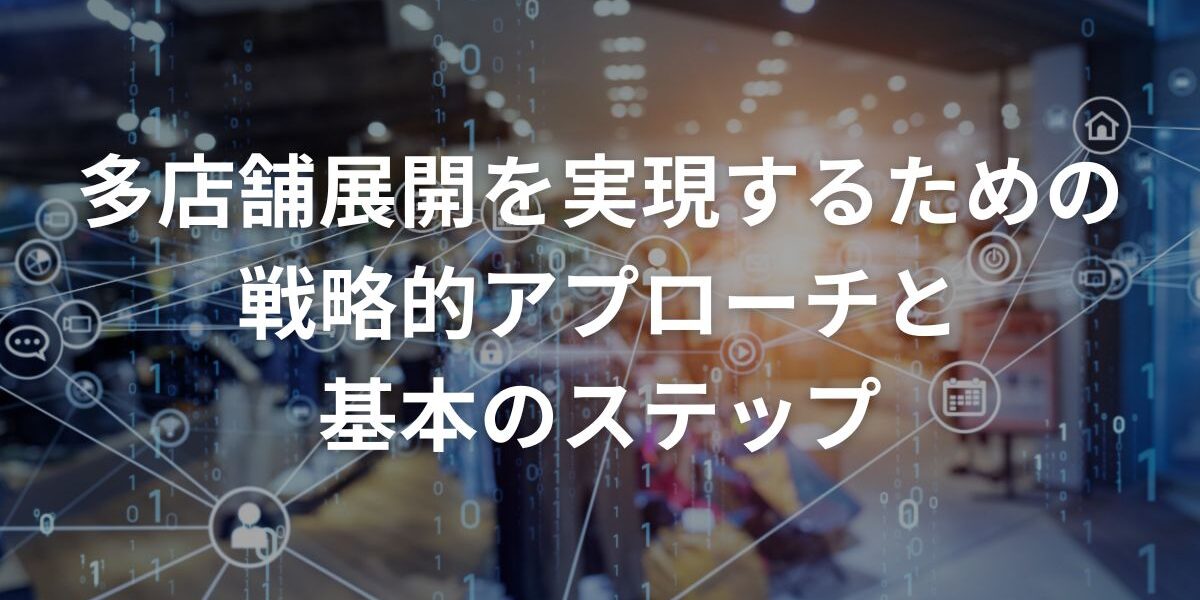
目次 ➖
多店舗展開とは、一つの地域にとどまらず、複数の地域や市場に複数の店舗を展開することで、顧客層を広げ、ブランド認知を高めることが可能です。しかし、多店舗展開は単に店舗を増やすだけでは成功を保証するものではありません。市場の特性や顧客のニーズを深く理解し、慎重に戦略を練ることが求められます。
この記事では、多店舗展開を成功に導くための基本的な考え方やステップ、そしてメリットとデメリットについて詳しく解説します。特に、どのようにして新しい店舗を選ぶべきか、効果的なエリアマーケティングを行う方法、そして人材の採用と育成における重要なポイントを紹介します。
これから多店舗展開を考えている企業や、すでに戦略を練っている企業にとって、この記事は参考となると思いますのでぜひ最後までご覧ください。
出店戦略にAIを活用するメリットとは?
従来の出店方法との違いはこちらから確認
→資料を見てみる
多店舗展開とは、企業が複数の店舗を異なる地域や市場に設置し、事業を拡大させる戦略のことを指します。このアプローチは、単一店舗での運営に比べて、広範囲な顧客層にリーチできることが大きな特徴です。多店舗展開により、企業は地域ごとの消費者ニーズに対応しながら、ブランドの認知度を高めることができます。また、複数の店舗を持つことで、経済的規模のメリットを享受し、仕入れや物流におけるコスト削減が可能となります。
さらに、多店舗展開は、リスク分散の観点からも重要です。異なる地域や市場での展開は、一つの店舗や地域での不調が全体の業績に与える影響を軽減することができます。例えば、一つの店舗が自然災害や地域経済の不況に直面した場合でも、他の地域での店舗がその影響を緩和する役割を果たします。
しかし、多店舗展開には管理の複雑さが伴います。各店舗の運営状況を把握し、適切に管理するためには、効率的なマネジメントシステムが必要です。また、各地域の文化や規制に応じた柔軟な戦略を立てることが求められます。特に、ローカライズされたマーケティングやプロモーション活動は、各店舗の成功に欠かせない要素です。
無計画に店舗を増やすと、経営資源が分散し、ブランドの一貫性が失われる可能性があります。戦略的な出店は、各店舗の役割を明確にし、地域ごとの市場特性を考慮した最適な配置を目指します。これにより、顧客のニーズに応えつつ、効率的なオペレーションが可能になります。
戦略的な店舗展開の重要性は、まず競合分析の徹底から始まり、適切な出店エリア選定、さらにはブランドイメージの統一によって強化されます。これらの要素を組み合わせることで、企業は市場での競争優位を確保し、安定した成長を実現できます。また、戦略的な店舗展開は、経営者が意思決定を行う際に柔軟性を持たせ、変化する市場環境にも迅速に対応できるようにします。さらに、人的資源や財務資源の効率的な配分も重要で、これにより各店舗が持つ潜在能力を最大限に引き出すことができます。最終的に、これらの戦略が一体となり、多店舗展開の成功を支える基盤となります。重要なのは、ただ店舗数を増やすことではなく、各店舗が持つ役割を最大限に活かし、それぞれがシナジーを生み出すようにすることです。このように戦略的なアプローチを取ることで、企業は長期的な成長と持続可能なビジネスモデルを構築することが可能になります。
多店舗展開の出店戦略を効果的に立てるためには、いくつかの重要な考え方を理解することが必要です。
エリアマーケティングとは、新規出店時にその地域の商圏内で競合状況やターゲット層などを分析することを指します。実店舗の場合、ECサイトと異なり、来店する顧客の多くは店舗の近隣に限定されるため、商圏(Market Area)を明確に把握することが重要です。
商圏の広さは店舗ごとに異なり、扱う商品や業態によって変わります。例えば、コンビニやスーパーなどの日用品・食料品を扱う店舗は、近隣の顧客が中心となるため商圏が狭い傾向にあります。一方、専門店やアパレル店舗は、遠方からの来店も見込めるため、比較的広い商圏を持つことが特徴です。
エリアマーケティングでは、マクロ環境として人口統計や世代構成、昼夜の人口変動などを分析するとともに、ミクロ環境として地域住民のライフスタイル、競合店舗、エリアの特性なども把握し、総合的に判断することが求められます。
3C分析、4C分析、4P分析は、多店舗展開戦略を策定する際に有用なフレームワークです。
まず、3C分析は「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から市場を理解する方法です。顧客のニーズや嗜好を把握し、競合の強みや弱みを分析することで、自社の強みを活かした戦略を立てることが可能です。
次に、4C分析は「顧客価値(Customer Value)」「コスト(Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」の4つの視点に焦点を当てます。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 顧客価値(Customer Value) | 顧客にとってどんな価値があるか |
| 顧客の費用負担(Cost) | サービスや商品を購入するにあたり、顧客がどのような費用負担を負うか |
| 顧客の利便性(Convenience) | 顧客にとっての利便性に優れているかどうか |
| 顧客接点(Communication) | 顧客とどのような接点が持てるか |
これは、顧客中心のマーケティング戦略を立案するためのフレームワークであり、顧客が求める価値を提供し、コストを最適化し、利便性を向上させることが重要です。
最後に、4P分析は「製品(Product)」「価格(Price)」「場所(Place)」「販促(Promotion)」の4つの要素を管理することで、マーケティング戦略を構築します。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 製品やサービス(Product) | 商品やサービスそのものの価値 |
| 価格(Price) | 適正な価格かどうか |
| 場所(Place) | スムーズな流通が可能か |
| 販促(Promotion) | どのような販促が行えるか |
製品の魅力を最大化し、適切な価格設定を行うことで、ターゲット市場に効果的にアプローチします。さらに、販路の適切な選択と効果的なプロモーション活動を通じて、ブランドの認知度を高め、販売を促進します。
PEST分析は、外部環境を把握するためのフレームワークで、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4要素で構成されます。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 政治(Political) | 法律や規制の変化、税制改正などが新規出店に与える影響を見極める。 |
| 経済(Economic) | 地域の経済状況や消費者の購買力を把握する。 |
| 社会(Social) | 人口動態や消費者の価値観の変化を考慮する。 |
| 技術(Technological) | 新技術の導入が競争力強化につながる。 |
このように、PEST分析を活用することで外部環境を総合的に理解し、リスクを抑えつつ成長の機会を最大限に活用する戦略を立てることができます。
出店場所の決め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
出店場所を決める際の考え方や選び方のポイントが良くわかる内容となっています。
【出店場所の決め方】失敗を防ぐために重要なポイントとは?
多店舗展開戦略を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。
出店場所を決める際は、商圏調査を行い、競合状況や顧客特性を把握した上で慎重に選定する必要があります。特に、既存店舗との距離は重要なポイントです。
既存店舗と近い場合、商圏が重なり顧客の奪い合いが発生する可能性がありますが、一方で、従業員のシフト調整がしやすく、経営管理が行き届きやすいという利点もあります。そのため、商圏エリアを明確にし、適切な立地戦略を検討することが重要です。
逆に、既存店舗と離れた場所に出店すると、顧客の奪い合いは防げますが、商品移動やスタッフの応援が難しくなり、オペレーションの効率が低下する可能性があります。そのため、各立地のメリット・デメリットを総合的に考慮し、最適な出店計画を立てることが求められます。
商圏調査(分析)のやり方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
商圏調査の基本的な理解からその必要性、商圏調査の活用シーン、メリット・デメリット、具体的な手順が良くわかる内容となっています。
商圏調査(分析)のやり方がわかる!活用シーンや基本のステップも解説
次に、自分の店に来ている客は、いったいどこから来ているのか?商圏を把握する必要があります。理論上から商圏を把握する代表的手法には、「ハフモデル」などがあります。ハフモデルは、主として小売店舗の立地計画について、事前に集客力、売上高の予測を行うためのモデル式のことです。
実態調査による商圏の把握方法で一般的なものは、「来街者調査」、「買物調査」などがあります。商圏は、距離ばかりではなく、線路や川、橋などの物理的条件や自動車の渋滞などの時間的条件も影響します。たとえば、距離的に近くに店舗があっても、階段を上って線路を越える必要がある場合には、その店舗に来店する確率は少なくなると思います。
次のステップは市場調査です。ターゲットとする地域の市場動向、競合状況、顧客のニーズを把握し、出店の可能性を総合的に評価します。次に、最適な立地の選定です。立地は顧客のアクセス性やブランドイメージに大きく影響しますので、細心の注意を払って選びます。
多店舗展開を成功させるためには、各店舗のコンセプトとデザインが明確であることが重要です。この段階では、まずブランド全体のアイデンティティを再確認し、それに基づく統一感のあるコンセプトを設定します。これにより、どの店舗においても一貫した顧客体験を提供することが可能になります。
次に、そのコンセプトを視覚的に表現するデザインを決定します。デザインは、店舗の立地やターゲットとする顧客層に応じて微調整することが求められます。たとえば、都市部の店舗ではモダンで洗練されたデザインが好まれるかもしれませんが、郊外ではより親しみやすさを重視することが重要です。さらに、店舗の内装や外観だけでなく、照明、音楽、スタッフの制服などもデザインに含まれる要素です。これらを総合的に考慮し、一貫性と独自性を持つデザインを構築することで、ブランドの認知度を高め、顧客の記憶に残る店舗体験を提供します。
スタッフの採用と教育もこの段階で重要なポイントです。適切な人材を確保し、ブランドの価値観やビジョンを共有することが必要です。
店長候補は、店舗運営に関する販売、管理、スタッフ教育などのノウハウを習得しておくことが重要です。また、新たに採用するスタッフが即戦力となるよう、適切な教育を行う必要があります。そのため、既存店舗のノウハウを可能な限りマニュアル化し、教育に活用することをおすすめします。
さらに、マーケティング戦略を構築します。地域に特化したプロモーション活動やデジタルマーケティングを活用し、新店舗の認知度を高め、顧客を引き寄せます。最後に、継続的な評価と改善が欠かせません。各店舗のパフォーマンスを定期的に評価し、必要に応じて戦略の修正を行うことで、持続的な成長を図ります。これらのステップを踏むことで、多店舗展開を成功に導くことが可能となります。
店舗出店計画の立て方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
店舗出店計画の成功のためのポイント、そして効果的な手順が良くわかる内容となっています。
店舗出店計画の立て方とは?重要な要素や成功のポイントについて解説
多店舗展開には、企業の成長や収益拡大に貢献する多くのメリットがあります。
まず、複数の店舗を展開することで、地域や市場セグメントごとに異なる顧客層にアプローチすることが可能になり、顧客基盤の拡大が期待できます。これにより、売上の増加だけでなく、ブランド認知度の向上にも寄与します。また、複数店舗を持つことで、仕入れや物流のスケールメリットを活かし、コスト効率を高めることができます。例えば、まとめ買いや一括交渉により、仕入れコストを削減できる可能性があります。
さらに、複数の店舗を持つことで、特定の店舗での売上不振や市場の変動によるリスクを分散することができます。これにより、経営の安定性が増し、長期的な視点での事業運営が可能となります。加えて、店舗ごとに異なる戦略を試すことで、各店舗の成果を比較し、効果的な施策を他店舗に展開することができるため、全体的な経営改善が図れます。
また、従業員の育成やキャリアパスの多様性が増し、社内の人材定着率向上にもつながります。多くの店舗を運営することで、従業員にとっても様々な経験を積む場が増え、会社全体の人材育成にもプラスの影響を与えます。
それから、多店舗展開は企業の内部組織にも良い影響を与えます。多くの店舗を持つことにより、社内での昇進や異動の機会が増え、社員のモチベーション向上や定着率の向上が期待できます。これにより、企業文化がより一層活性化し、長期的に見て企業の競争力を強化することができます。
多店舗展開により、企業は顧客基盤を広げ、より多くの消費者にアプローチすることが可能になります。この戦略は、単一店舗ではカバーできない広範囲の市場ニーズに対応できるため、企業の成長を加速させる大きな要因となります。さらに、複数の店舗を持つことで、ある店舗での売上不振や市場の変動による影響を他の店舗で補うことができ、リスク分散としても効果的です。このように、多店舗展開は、企業が持続可能な成長を実現するための重要な戦略となります。
さらに、多店舗展開によって得られるデータは企業にとって貴重な資産です。各店舗の業績を比較することで、成功した戦略や改善が必要な点を見つけやすくなります。これにより、企業は効率的に経営判断を行い、より効果的な戦略を立案することが可能となります。多店舗展開は、単なる規模の拡大に留まらず、企業全体の成長戦略としての意義を持ちます。
多店舗展開には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべきポイントも存在します。
まず、経済的なリスクが増加する点が挙げられます。各店舗の運営には、賃料、人件費、在庫管理などのコストがかかります。これらの費用が増えることで、全体の利益率が低下する可能性があります。また、店舗が増えると、管理の複雑さが増し、オペレーションの効率を維持するためのシステムの整備が必要になります。この際、各店舗間でのコミュニケーションが不足すると、ブランドの一貫性が失われるリスクもあります。
さらに、地域ごとの市場特性や消費者の嗜好を無視した展開を行うと、期待した成果が得られない可能性があります。このため、各地域の市場調査をしっかりと行い、それぞれの店舗に適した戦略を立てることが重要です。
最後に、競合他社との差別化が難しい場合、価格競争に巻き込まれるリスクがあります。このような状況を避けるためには、独自の価値を提供し続けるための継続的な努力が求められます。多店舗展開を成功させるためには、これらのデメリットを踏まえた慎重な計画と実行が不可欠です。
多店舗展開で成功している経営者の多くは、まずドミナント(近隣集中出店)戦略を採用しています。これは、すべての店舗が経営者の目の届く範囲にあり、一日で訪問できる距離に配置されていることを前提とした戦略です。
多店舗展開を目指す場合、まずはドミナント戦略を活用し、管理しやすいエリア内に店舗を展開することをおすすめします。この戦略により、マネジメントの効率化やブランド認知の向上が期待でき、成功の確率も高まります。ただし、店舗同士が顧客を奪い合う「カニバリゼーション(共食い)」を防ぐため、適切な出店計画を立てることが重要です。
さらに、多店舗展開戦略の成功には、AI導入などの技術革新が不可欠です。まず、AIを活用することで、在庫管理や顧客データ分析が効率化され、各店舗の運営をスムーズに行うことができます。具体的には、顧客の購買パターンを分析し、最適な商品を最適なタイミングで提供することが可能になります。また、AIによる需要予測は、無駄な在庫を削減するだけでなく、売り上げを最大化するための重要な手段となります。
さらに、チャットボットの導入は顧客対応を24時間体制で行うことを可能にし、顧客満足度の向上に寄与します。これにより店舗スタッフは、より付加価値の高い業務に集中することができ、全体的な業務効率が向上します。
加えて、IoT技術を活用した店舗内センサーは、来店客の行動をリアルタイムで把握し、店舗レイアウトや商品配置の最適化に役立ちます。これにより、顧客体験が向上し、リピーターの増加につながります。
技術革新を積極的に取り入れることで、多店舗展開における競争優位性を確立し、長期的な成長を実現することができるのです。したがって、これらの技術をどのように自社の戦略に組み込むかが、多店舗展開の成否を分ける鍵となります。技術の導入には初期投資が必要ですが、長期的な視点で見ればその価値は計り知れません。
多店舗展開の出店戦略にAIを活用してみませんか?
サポート体制も整っているため、安心して運用できます
→資料を見てみる
多店舗展開の出店戦略を成功させるためには、以下のような計画と実行が不可欠です。
このような戦略が整えば、顧客のニーズに迅速に対応できる体制を築くことができ、店舗間のシナジー効果を最大化することができます。多店舗展開は、単なる店舗数の増加を狙うだけでなく、全体としての企業価値を高めるための重要な施策です。適切な戦略を策定し、実施することで、長期的な成長と持続可能なビジネスモデルの構築が実現します。各店舗が地域に根ざし、顧客に愛される存在となるための努力を惜しまないことが、企業成功の真の要因となるでしょう。